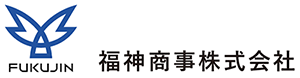令和7年6月17日
税務調整
改めて税務調整について話していきます。会計上は「収益―費用=利益」となりますが、税務上は「益金―損金=所得」が公式となります。前にもお話しました当期純利益がスタートです。そこから収益から益金、費用から損金へ変えていく事が税務調整となります。収益だけど益金に算入するもの、算入しないもの、費用だけど損金に算入するもの、算入しないもの、4つがあると話しましたが、本日は収益として認識していないが、益金として認識するものを学んでいきます。
この代表的なもの、先ず一つは、無償取引や無償譲渡となります。どういう事かというと、会社の資産、現金から始まり、商品や不動産、こういった資産を他人に無償であげる事です。ここだけ聞くと気前のいい話ですが、何故そんな事が起こるのかというと、親会社と 100%子会社等の場合、子会社がうまくいっていない時、その資産を増やそうという事で現金をあげたりと無償で譲渡する事があり得る訳です。ただ、そういった無償であげた場合に、税務上どの様になるかですが、収益上は0で、売上がたたないから税金も発生しませんとはなりません。税務署がそんな事を認めていたら税金を払わないで、どんどん自分の資産を減らす事が出来る訳です。この資産は第三者に売ったら必ず利益が出て、税金が掛かってくる。それは馬鹿馬鹿しいから無償で譲渡しようとすれば、その会社は税金払わないで資産減らす事が出来ます。それはよくないという事で、税務の世界ではこの取引、この無償譲渡でやったものは益金に算入します。仮に 100 の資産があるものを無償で売却したら、収益的には 0 です。仮に費用が 0 で差引、所得が100 だとするならば100 に対して税率が掛かってくる。これが収益ではないが益金算入となる例です。
他に何があるか、古い言い方で低廉譲渡、今はそんな言い方はしませんので、皆さんは低額譲渡で覚えて下さい。例として、時価が1 億円で、簿価が3,000 万円の資産を 7,000 万円で売却するといった場合、A 社は4,000 万円の利益が出て、税率が 30%だとすれば1,200 万円の税金が掛かってきます。税務署がそれを許すのかというと決して許しません。7,000 万円で譲渡しても、これは時価が1 億円だから簿価を差引き、7,000 万円の利益で30%の税率をかけて2,100 万円の税金を払って下さいとなります1,200 万円でいいのかと思っていたら、差引900万円の追徴課税が来るという事です。これが、収益ではないが益金にしますという2つ目の例です。
もう一つは棚卸、商品管理とか、商品在庫です。棚卸を何故するかというと原価をはじく為です。棚卸をして、仮に100だったとします。査定して、それで収益は100、こういう計算で終了していた訳です。ところが、この在庫っていうのは、商品もそうですし、製造業であれば、製品それから半製品、要するに作りかけの段階の製品、もっと前は材料とか色々な呼び方がありますが、それらは全部在庫に含まれる。税務署は、税務調査に入ると工場なり倉庫なりの在庫を調べていきます。そこで半製品とか材料も加えてプラス5だとなったら、貸借対照表上では左方の資産を増やす、すると右方のどこを増やせばいいか、資本、つまりは利益を増やします。商品の在庫を増やすと利益が増える、その増えた分については、修正しますという事で税務署は追加で税金を取る事になります。
収益ではない益金算入
i) 無償譲渡(取引)→子会社などに無償で金銭を譲渡等
ii) 低廉譲渡(低額譲渡)→時価s100、簿価30を70で譲渡すると
40の利益100-30で70に対して税金となる
iii) 棚卸残高
完成品・半製品・材料
B/S上で商品を増加する場合、P/Lで利益が増える→税金が増える
次の項目で、収益ではあるが、益金不算入について話していきます。これは寧ろ税金を払うという立場からは有難い話となります。皆さん方、もう覚えていると思いますが、代表的な例は配当金です。ここでは細かい事は言いませんが、配当する場合、その原資は税引後の利益の中から配当するのです。すなわち既に税金は取られています。それをまた配当収入として計上すると、また税金を取られる。すなわち二重課税となります。この二重課税の考え方は税務署も容認しております。配当金もその出資状況によって不算入率が違ってきますという話は以前にもしました。これが益金不算入になる代表例です。
次は法人税が還付された場合です。法人税が還付されるというのはどういう場合かというと、資本金1億円以下の中小企業に限って、1回限りという条件になります。前期1億円の利益が上がったと、単純に1 億円掛ける30%の実効税率として、3,000 万円の税金が発生しました。1年たって当期はどうなったかというと5,000万円の赤字になったとします、税金は0で終わりですが、こういう場合に、企業には継続性の原則がありますので、中小企業に限り、かつ1 回に限り還付しますといったものがあります。どういう風に計算するか、前期と当期を合算します。1 億円に対して赤字が5,000万円ですから、合算すると通期で+5,000万円の利益となります。この利益に対して 30%の税金をかけると1,500万円の税金と計算されます。この企業は前期3,000万円税金を払っており、通算すると1,500万円でいいとなっている事から、差引1,500万円が還付される訳です。これが益金不算入にどういった関係があるかというと、要するに還付であっても現金が入って益が出る訳です。会計上は収益としてあげますが、税務上これを入れてしまうと二重課税になる訳です。益金不算入は、殆どが配当金ですが、法人税が還付される場合もあり、これは難しく考えず、法人税還付された場合はその還付されたものにまで税金をかけることはないと覚えて貰えればいいです。
もう一つ受贈益というものがあります。今日はもうこれで終わりにするので、次回はこの受贈益から始めたいと思います。これは本日話した無償譲渡した場合に、例えば中小の100%子会社に対してそういうものをやったら、それを受けた方が受贈益として収益認識をしなくてはいけません。そこからどういった事になるのかというのは次回から話していこうと思います。
収益ではあるが益金不算入
i) 配当金→二重課税
ii) 法人税還付分→中小企業に限り、かつ一回限り←前期が黒字で今期が赤字の場合
還付されたものに税金はかからない程度の認識でよい
iii) 受贈益→無償譲渡を受けた側
以 上