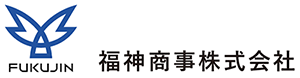令和7年4月15日
グループ通算制度
いつも同じ様な事を話していますが、繰返し繰返し聞いている内に段々と慣れてきます。その内、ああこういう事かと理解出来る様になり、そうなると、「どこかで同じ様な言葉を聞いたな。」という事で知識と結びつく形となります。法人税というものは特殊な考え方をしますから、始めにゴーイングコンサーンという企業の永続性について話し、次に法人擬制説と法人実在説を話しました。そして、今日の講義がグループ通算制度となります。
先に復習をしておきますと、ゴーイングコンサーンという、企業は永遠ですといった意味がありますが、企業経営を続けていくうえで赤字になると欠損金というものが生じます。この欠損金というものは黒字決算の時、相殺が出来ます。本来黒字の場合、税金を支払う訳ですが、赤字が続き欠損金がある場合、相殺する事で税金を支払わなくていいというものです。青色申告が大前提ではありますが、中小企業の場合はこの欠損金の範囲で10年間の利益相殺が可能です。赤字企業に対して非常に温情的なのは、やはりゴーイングコンサーンというものの考え方があるからです。税務署としてもこの理論に基づいて中小企業の健全な育成に寄与しているわけです。次に法人擬制説と法人実在説の話を前回しました。実在説は会社というのは、独立した個人の人間と同じ様に法人というのも実際に存在するものという考え方で、この実在説を取る国も非常に多くあります。もう一つの法人擬制説は、法人はあるけど実態はなく、責任を取れる人が誰かと言ったら株主なので、法人とは株主のものですよという考え方で、日本は法人擬制説をとっております。生み出した利益に対して税金を取られた後、当期純利益の中から配当が出て、配当を貰った人が配当金を収益に上げると、その利益に対して税金を掛けられ、同じ財源から2回税金を支払う形になってしまいます。所謂二重課税というものは禁止されていますから、配当金は益金不算入とする必要があります。しかしその不算入率は配当を出す側と受け取る側の関係で決まってきます。
改めて今日はグループ通算制度について話をしていく訳ですが、これは親会社と子会社の関係における制度です。子会社といっても100%出資子会社もあれば50%、20%もあり、ここで言う子会社というのは100%子会社となりますが、グループ法人税制を説明する前に、一つ常識として会計上での歴史的な背景を話していきます。今から20年位前となりますが、親会社が赤字で子会社が黒字だった場合、ある程度特殊なケースですが、親会社は自分を良く見せる為に、この赤字を子会社に付け替えた事例があります。そうすると、親会社の決算っていうのは本来より良く見えます。こういう決算が流行った時代が過去にはありました。特に上場会社でこの様な事をするのは株主を愚弄するようなものです。投資しようとする人は、黒字決算の良い会社だと思ったら、実際は赤字でその赤字は子会社に計上されていたというのは常識的にやってはいけないというのは当たり前です。
会計上は単体決算が原則ですが、それだけだと、子会社に赤字を付け替えたりといった悪い事をする人がいる事から、上場会社たるもの100%子会社と連結した決算をするよう証券取引所の規則が改正されました。だから会社四季報を何回かご覧になった方は判ると思いますが、子会社を持つ会社の場合、単体決算と連結した決算の2 本立てになっています。では、我々が勉強している税制面はどうなっているのかというと、例えば単体で親会社が100の利益、子会社が200 の赤字だった場合、単純に実効税率30%で考えた場合、親会社の税金は30 ですが、連結として考えた場合、両方足したら赤字となりますので、税金を支払わなくてよくなる訳です。この様に100%子会社で完全支配関係の場合に「グループ通算制度」が使える訳です。このグループ通算制度は連結していれば無尽蔵にやっていい訳ではなく、国税庁長官の承認を得る必要があります。申請し、許可されれば連結納税が出来る仕組みとなっております。なので、これは上手いこと聞いたと、今期はこことここが赤字だからこれを連結しよう。来期になったら両方とも黒字だから黒字になったから単体決算でやろうというのは出来ません。一旦この承認を得たら、半永久的に連結納税する形となります。
受贈益
以上がグループ法人税制となりますが、親会社と子会社の関係はそれだけではありません。これはこれで一つ理解して頂き、もう一つは、通算制度とは別に、「受贈益」という言葉があります。これは何かというと、子会社が大幅な赤字でこのままでは、立ち行かないという事で、親会社が例えばキャッシュで1 億円あげましょうといった時、受け取った子会社は受贈益に、親は無償であげる訳ですから、こういう行為は寄附金の勘定科目で計上します。一方、子供は受贈益と言う益金となります。この受贈益は益金不算入となり税金がかからない仕組みとなっており、これがいわゆる100%子会社の受贈益の考え方になります。子会社が困っていて、親会社から1 億円お金をもらったら、そこに税金が掛かって、3 割持っていかれて7000 万円しか利用出来ないというのは可哀想だと言う事で、1 億円をそのままそっくり使えるというのがこの受贈益の益金不算入制度なのです。
このグループ法人税制やゴーイングコンサーン、二重課税から法人擬制説等々、特殊な考え方を色々と学んできました。これを受けて、これから各論に入っていく訳ですが、もう一度振り返ってみて税務と会計の根本的な違いは何なのかと言うと、まず会計というのは、ステークホルダー、つまり取引先や株主、銀行、仕入先、販売先等の利害関係者や世間一般の人達も含めた人達に会社の状態を知らせるのが会計の目的となります。
税務は会計で出た利益に対して税金を掛ける訳ですが、公平性が一番重要となります。公平性と同時に政治的な思惑や、事情を勘案しないといけないのが、会計と違うところです。これから各論に入っていく事で、公平性や政治的思惑と企業会計原則との違いについて学んでいきます。各論を説明していく上で、また同じ言葉が出てきますので、あまり心配せずに出てきた言葉に慣れて貰いたいと思います。本日はこれまでにしておきます。
以 上