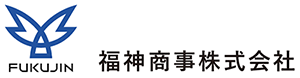令和7年7月15日
税務調整
遅々として進まない中で、前回から1ヵ月2ヵ月と経つと最初の頃に学んだ事を忘れてしまっているかも知れませんが、会計上と税務上の違いというものに慣れて頂きたいと思います。会計上は収益―費用=利益の方式で出しますが、税務上は言葉が違います。収益費用とは言わないのです。収益は益金、費用は損金と言いますので、繰り返しになりますが、この言葉にも慣れて下さい。勿論利益も同じ言い方はせず、所得と言います。収益を益金に、費用を損金に利益を所得にしていく事が税務調整ですが、この過程を通るには大前提として企業会計原則があります。原則に基づいて利益を出す、この当期純利益が税務調整をする決算書別表4の出発点となります。何を言いたいかというと、税金を納めたくないからと決算で利益を少なくする、仮にそういう企業があったとすると、それは粉飾決算と言って、企業会計原則に基づいていないので受け取れませんとなる訳です。こういった税務調整に係る法人税特有の思考過程を整理していきたいと思います。
<法人税特有の思考過程>
会 計 収益 ― 費用 = 利益(当期純利益)
↓①② ↓③④
税 務 益金 ― 損金 = 所得
① 収益NO→益金算入
② 収益YES→益金不算入
③ 費用NO→損金算入
④ 費用YES→損金不算入
大前提は正しい決算をする。これが一番大事です。正しく当期純利益を出す事が起点となっていて、上記の様に収益から益金、費用から損金とするこの矢印の①②③④が税務調整であり、決算書の別表4に係るものとなります。他にも色々ありますが、中心になるものはこの別表です。繰り返しますが、収益認識はしていませんが、税務上の益金には算入します。収益認識はしているが益金には入れないでいいですよ。費用認識はしてないけども損金には算入します。最後に費用だけども損金に入れないでいいですよという4種類の事をする訳です。この税務調整が、法人税を理解する上での肝となります。税務署側でこれが正しく計算されているかの出発点となるのが株主総会を経て確定された資料かどうかで、監査役の証明がないと受け付けません。この確定申告書を決算後2ヶ月以内に提出し、税金を納めるまでがセットで一連の流れとなります。各税務調整についてはこの後細かく説明していきたいと思います。
それぞれ例を挙げると、①収益ではないが益金となるもの、企業にとっては税金を多く払う事になるのでマイナスのものです。例として、無償譲渡等が挙げられます。所有する資産を相手へ譲渡する、例えば時価7,000万円の不動産を無償で譲渡した場合、収益は0でお金が入ってこないのだからしょうがないとはならない。税務ではそれを許しません。この例では実際の売買価格ではなく時価で売買したものと見做し、その分を益金へ算入する税務調整が行われます。
②の収益だが益金へ算入しないものについては配当金や還付金、受贈益等が挙げられます。配当金は税引後の純利益から算出する為、受け取る側で再度益金として認識すると二重課税となってしまいます。細かい事は色々ありますが、二重課税禁止の原則から配当金は益金不算入となります。還付金は企業の継続性の原則(ゴーイングコンサーン)という考え方から、1 期目が黒字で税金を払ったが、2期目で赤字となった場合等に通算して支払う金額が計算され余剰分が戻ってくる、つまり還付されるお金の事です。受贈益という言葉は初めて聞く方も多いと思います。受贈益は、かく言う私も社会人になって20年30年経って初めて聞いて、「なんだそれは。」となった位なので、皆さんがこの段階でこの言葉を聞いている、理解しているというのはレベルとして凄い事なのです。大学で会計を学んで卒業した人達でも、こういったものの考え方がきちんと頭に入っている方は5%もいないんじゃないかなと思います。受贈益は無償譲渡等で資産を譲受した場合の利益ですが、受け手側が100%子会社(完全支配関係にある)の場合のみ益金不算入となります。しかし一般企業では益金認識となりますので注意してください。
③は費用ではないが、損金へ算入する例として、繰越欠損金が挙げられます。例えば初年度で1,000万円の赤字が出た場合、毎期100万円の利益が出ても繰越欠損金という制度を10年間適用でき、税金を支払わなくて済むといったものです。但し、資本金1 億円以下の中小企業に限ります。大企業も適用期間10年は同じですが、中小企業と違い50%までとなっております。これらは税制の変化によって変わってくるものなので今はこの割合となっています。私の記憶上では過去に25%とか30%なんていう時代もありましたが、10年以上に伸びた事は記憶にありません。
④は一番身近なものかも知れません。費用だが損金へ算入出来ないものの例としては、交際費・寄付金・減価償却費・役員報酬等が挙げられます。特に分かり易いのは交際費で、儲かって儲かってしょうがない企業が税金を払いたくないからと銀座で接待としてお金を使いまくって極端な例として赤字になってしまえば税金を支払わなくてよくなってしまいます。なので交際費には大企業を除いて損金算入限度額が決まっているのです。私なんかも当時、交際費としてお酒を飲んでいたりした時に、1ヵ月で100万円使ってそれで済むと思ったら大間違いで、その実行税率分 30%としたら30万円税金でお金が出ているからあなたは 130万円使ってるんだよ、なんて経理に言われた事もありました。中小企業であれば年800万円までは損金に算入できます。
ここでの税務調整は大きく上記の 4 つで、その細かい事例も併せて本日は話していきました。こういった一つひとつの言葉を覚えて頂き、今後に活かして頂ければと思います。
以 上